安曇川沿岸の農業
琵琶湖の起源は400万年前にさかのぼる世界でも数少ない古代湖である。湖の周りは数万年から人間が住み、肥沃な土地に恵まれ、独自の稲作文化を培って来た。
日本の稲作は、2千数百年前朝鮮半島より伝わり、弥生文化を生み出し、優れた稲作技術により古代国家を形成してきた。その後、律令制と荘園制の時代(700年~800年代)は、国の基盤を作り条里制を敷き、水路、道路を整備し水田の基盤を形成してきた。
安曇川は京都単語の百井峠に源を発し、朽木盆地を縦断し北川を始め各支流を集める県下第2位の河川で、その延長は57.9km、流域418.9k㎡で琵琶湖へ流下している。
安曇川のデルタは、縄文遺跡や弥生遺跡が見られ、縄文遺構は新旭町大字安井川にあり弥生遺跡は安曇川町大字田中下ノ城南堀遺跡、更に新旭町饗庭や深溝など各地に見られる。また、大化元年の班田収授法(646年)による条理制の遺構が見られ、歴史の古さを物語っている。近世になってから、開墾や開拓が盛んで用水や排水等の工事が進められてきた。
この河川はときには南に、あるいは北へ洪水のたびに移動し、山から肥沃な土を運び現在のデルタを形成してきた。この扇状地上流部は、本流から取水することが容易で、稲作農業としては最適な条件で、中下流部は、沼や湧水池が多く湿田である一方で、河川の水量の変動が激しく中流部の水田は水不足に悩まされ度々水争いが生じている。
安曇川デルタ地帯の水の供給源は、そのほとんどが安曇川に依存し、堰により取水した表流水のほか、伏流水として地下に浸透し豊富な水が湧水として湧き、農業用水のほか、伏流水として地下に浸透し豊富な水が湧水として湧き、農業用水のほか、生活用水や産業用水などの地域の環境用水として様々な利用がなされている。
農家の経営面積は、明治以降も積極的に開田が行われ耕地面積も増加した。戦後は食料増産により、湖西地域の最大の穀倉地と、近江の特産「早場米」の産地を形成してきた。しかし、1970年代になり日本経済の急激な発展に伴う食生活の変化により米の消費が減退し、在庫過剰により米の生産調整が開始された。
1972年(昭和47年)琵琶湖総合開発により土地改良関連事業として、水源の見直しと、ほ場整備事業の着手により、農業の生産基盤は大きく変貌し、改良区の受益区域と面積に大きな変化が生じた。さらに近年では、世界経済の発展と自由貿易の発展を受けたガット・ウルグアイラウンド農業合意により、一段と厳しさが増し水田農業として大きな転換点を迎えている。
安曇川沿岸農業水利の歴史
安曇川の流域は、花折断層安曇川の流域は、花折断層が走る比良山系の狭い流域で、水量の変動が激しく、安定した取水が非常に困難であり、古くから水争いが絶えなかった。
1770年代の安曇川の取水は、両岸に用水井堰が8ヶ所あり、左岸は二番井、五番井(饗庭井)六番井(北畑井)八番井(新庄井)の4ヶ所で、右岸は、一番井、三番井(三重生井)四番井(田中井)七番井(本庄井)の4ヶ所、計8ヶ所12ヶ村となっている。
しかし、その水争いの歴史は古く、1721年(享保6年)田中井13ヵ村の下流東萬木村、島村が田中井に加入したいと京都区役所に訴え、また、1770年(明和7年)かんばつが続き深溝村と霜降村との争いがあり1771(明和8年)京都区役所に訴えた。また1774年(安永3年)饗庭井修繕費の争い等多くの訴訟が行われている。
1950年(昭和25年)安曇川合同井堰改修前の旧井堰の数は、右岸5ヶ所(広瀬井、須寺井、三重生井、田中井、青柳井)と、左岸6ヶ所(高畑井、下古賀井、川原井、饗庭井、北畑井、新庄井)の11箇所2530haの受益地区となっている。
1949年(昭和24年)ヘスター台風により旧井堰が流失し、1952年(昭和27年)県営災害復旧事業として合同井堰の工事に着手した。1953年(昭和28年)13号台風によりさらに被災が拡大した。このため、災害復旧事業と災害関連事業ならびにかんがい排水事業の合併により、当初計画された事業計画に沿い着手された。その受益面積は、安曇川町1420ha、新旭町1111ha、合計2531haの事業着手となった。
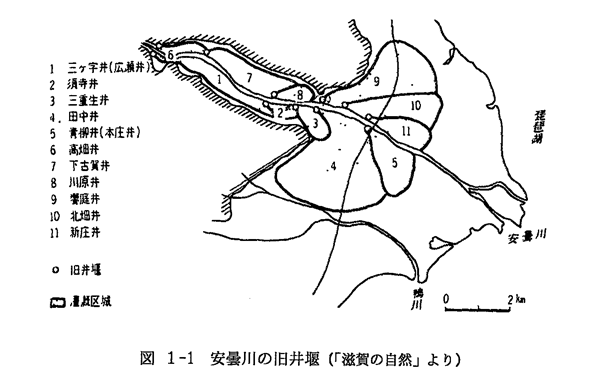
1957年(昭和32年)米軍によるあいば野演習場の接収が解除されたが、饗庭野の保水力が低下し用水が激減する一方、降雨時には土砂が流出し演習場周辺農地に被害が生じていた。
このため、用水源の復元と農地の保全について国に要望した結果、水源施設として安曇川演習場内「一ノ瀬川」にアースダムを築造し、導水路を新設改修し用水確保と被害防止を図ることを目的とした県営障害防止対策事業が認められ1966年(昭和41年)事業に着手された。
1972年(昭和47年)先に述べたとおり、琵琶湖総合開発により土地改良関連事業として水源の見直しと生産基盤の整備計画が樹立され、当改良区安曇川頭首工かんがい区域の大幅な変更が生じた。
記念誌「水と土50年の歩み」より
