
1949年(昭和24年)のヘスター台風で9ヶ所の井堰が流失し、これを契機に井堰を統合した合同井堰を築造することとなった。
1952年(昭和28年)の台風13号によりさらに被災が拡大したため、災害復旧事業と災害関連事業ならびにかんがい排水事業の合併により、当初計画された事業計画に沿って着手された。合計2531haの事業着手となった。
合同井堰で取水した水は、隧道によりこの分水工へ運ばれます。そして分水された右側の水は、まっすぐに左岸幹線用水路へ、また左側の水は伏越工で2本の横断管により安曇川の下を潜り、右岸用水路へ送られます。
固定堰には魚道堰の変位を防止する働きと、形状を弧状にしたことにより「滝」のイメージを持たせ景観に配慮しています。
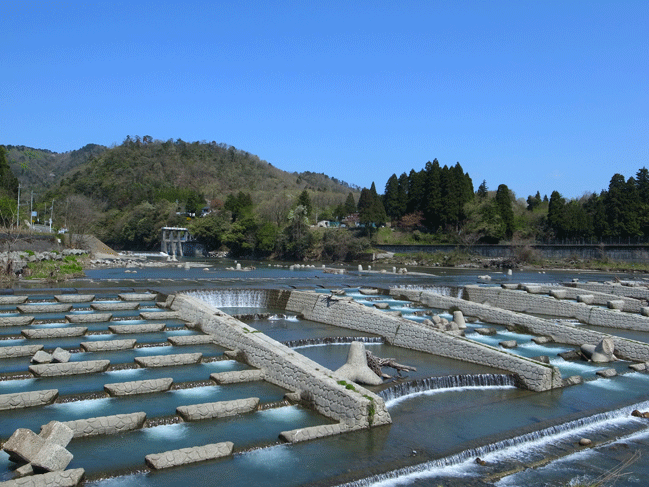
一級河川安曇川の河床低下から農業用施設(安曇川合同井堰とその下流の横断する樋管)を保護するため床止工が設置されました。
この床止工には、自然との共生を目指し、周辺水域に生息する多様な水生物が自由に移動できるように全面魚道を採用しています。
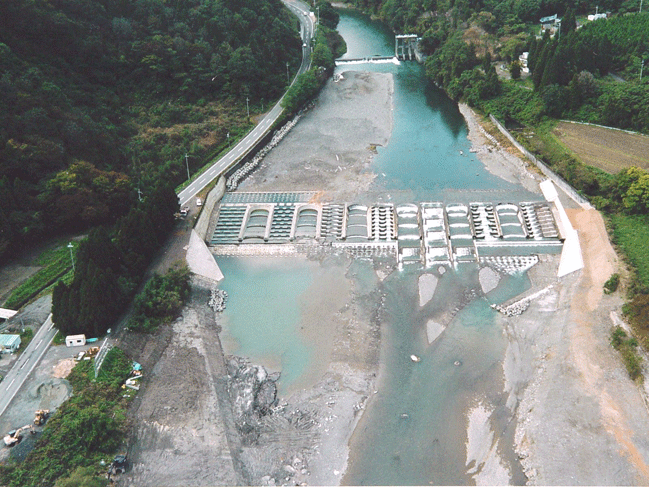
1963年在日米軍補償工事事業(あいば野地区)奥山ダム計画が採択となり、1964年度より着工なりました。なお、この事業の着工にともない長年懸案となっていた、当初計画のかんがい排水事業「麻生ダム」の施行については断念することとなった。
円形分水工
右岸幹線用水路の南古賀につくられた円形の分水工です。ここで鴨川幹線用水路方面と青柳・十八川・三重生幹線用水路方面へ分水し送水されます。
3号分水工
左岸幹線用水路の井ノ口地先にある扇形の分水工です。ここで五十川、米井、井ノ口方面と新庄、北畑方面へ分水し送水されます。
